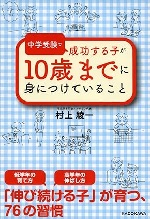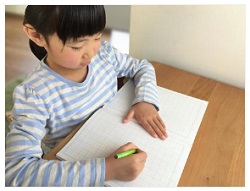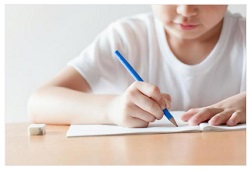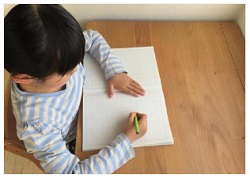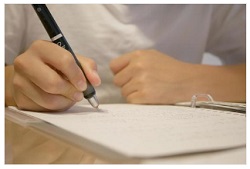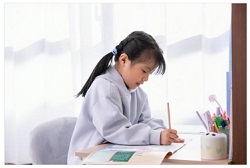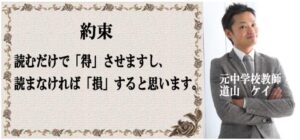理数系専門塾エルカミノ代表の村上綾一さんが、著書「中学受験で成功する子が 10歳までに身につけていること」で図形問題への対処法を解説されています。
図形問題に強くなるには勉強というより、小さいころからの”遊び”がモノを言うようです。
同書の156~159ページから一部抜粋して紹介します。(この本は参考になりますよ!)
苦手な子が多い図形問題 小さい頃からフリーハンドで絵を描いてみる
図形問題を苦手とする子供は多いようです。
中学受験で子どもたちが苦手としている問題に、図形があります。
実は図形問題は、頭の中で考えられれば速く解けます。しかし、小学生には難しい。
そこで、図形を描いて、目に見える形にして考えるように教えています。
図形問題を苦手にしている子どもたちは、この図を描く作業が苦手です。
絵を描くならフリーハンドがオススメです。
慣れないうちは定規を使ってもいいですが、フリーハンドで描くことのメリットは忘れないようにしましょう。
図形問題の苦手克服の第一歩として、図を見て描く練習をしましょう。これが意外に難しいのです。
最初のうちは、立体を写すときに必ず使う斜めの線が描けません。上から下に、垂直の線を引いてしまうのです。
ちなみに、幼少期に絵日記をつけていた子どもは、立体を描く経験を積んでいるので、図を描くことにも、比較的抵抗なく入っていけるようです。
初めのうちは、図を描くときに定規を使ってもかまいません。描き慣れてきたら、フリーハンドで描きます。
実は定規を使っていると、定規で引いている線しか見えません。全体が見えないのです。
一般に、道具を使うと、そこに神経がいってしまうのと同じです。
フリーハンドで描いていれば、全体が見えます。フリーハンドで練習しているうちに、やがて頭の中で立体図形をイメージできるようになっていきます。
図を描く=絵を描くですから、普段から慣れておくと有利なのは当然です。
どうしても描けない場合は、次コンテンツで紹介する村上さんの「とっておきの練習法」を参考にしてみて下さい。
- PR:Amazon 村上綾一さんの本
1日10分で大丈夫!「自分から勉強する子」が育つお母さんの習慣
理系脳をつくる ひらめきパズル
新版 面積迷路(学研ムック)
1駅1問! 解けると快感! 大人もハマる算数パズル

苦手なら方眼紙を使うのもアリ 村上さんおすすめの練習帳は
村上さんはこうした練習法を勧めています。
練習の初めは、白紙よりも方眼紙を使うほうがいいでしょう。
ここでおすすめしたいのが、「思考力算数練習帳シリーズ13/点描写(立方体など)」(M.access編/認知工学刊)。
点が打ってあるところに、図形を描く練習をしていきます。
この練習帳は大人にもおすすめで、なかなかの歯ごたえです。
PR:Amazon思考力算数練習帳シリーズ13 点描写(立方体など)
補助線引きはセンスでなく経験がモノをいう ここでも絵を描く力が
図形問題を解くキモのひとつに補助線があります。
「ここに引くと良い」と気づくにはセンスの良い子が有利に思えますが、村上さんは「補助線を引くのにセンスはいらない」としています。
代わりに必要なのは…
図形問題を解くときによく使うのが補助線。
補助線が引ければ、それまで見えなかったものが見えてくるので、答えにグッと近づきます。
しかし、補助線を引くこと自体が難しいもの。補助線がうまく引けるか引けないかは、センスだと考える方も多いのですが、センスではなく経験にほかなりません。
わからなかったら、とりあえずおさまりがいいところに引いてみましょう。
ここに一本あったらスッキリするな、という感覚でいいのです。こうしてトライしているうちに、だんだん引けるようになっていきます。
補助線も、図形を描き慣れている子どものほうがためらいなく引けますし、引く箇所を見つけるまでが早いのは言うまでもありません。
図は、すぐには描けないものです。幼少期に親子で楽しんだ習慣、たとえば絵日記やお絵かきなどの遊びを通して、力を蓄えておきましょう。
PR:Amazon
立方体の切断の攻略